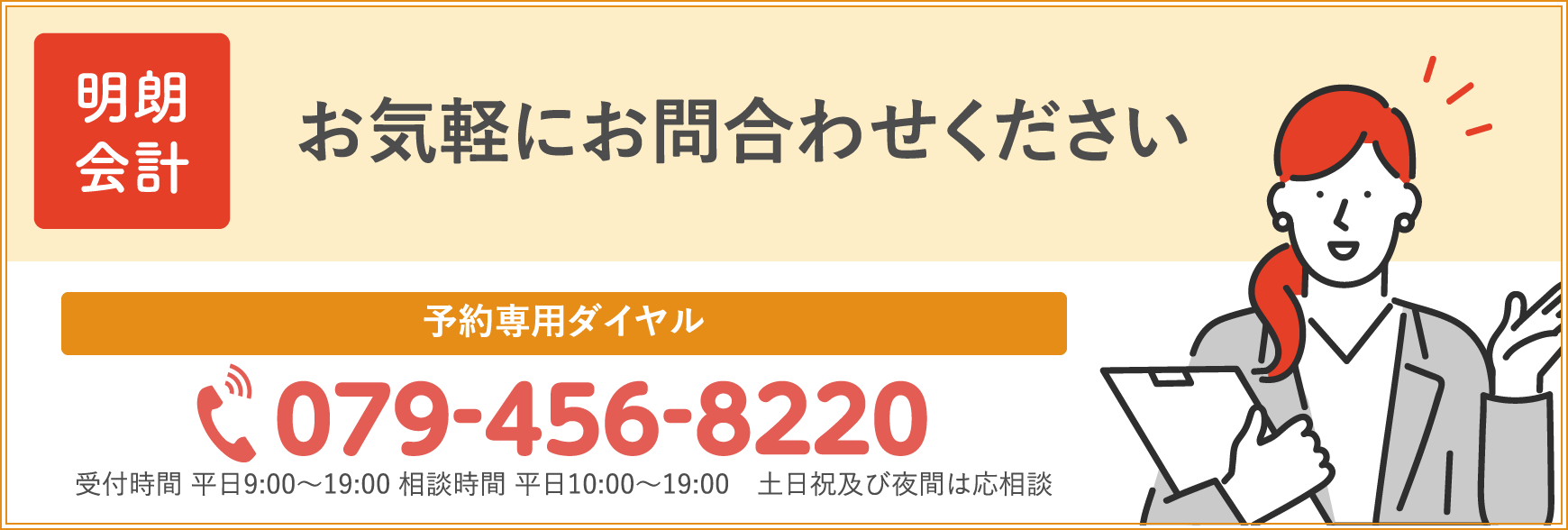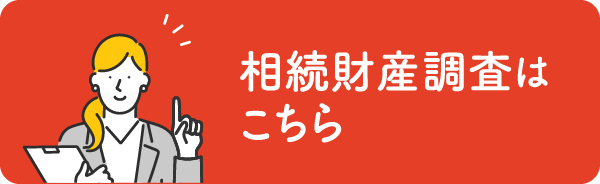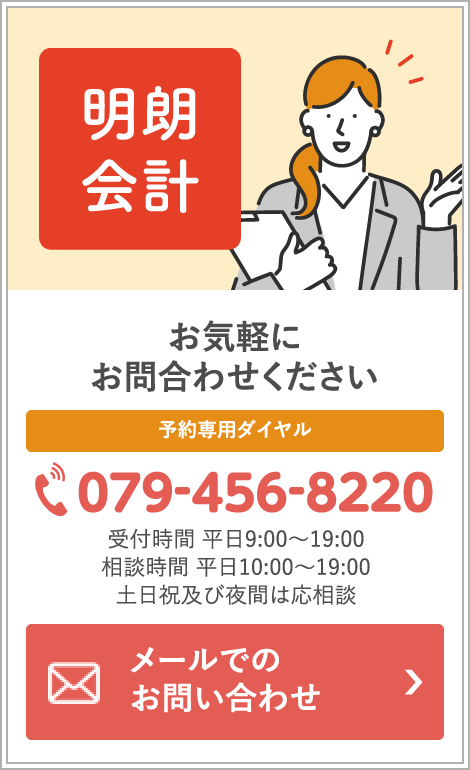面識のない相続人、行方不明・音信不通の相続人に相続放棄はさせられますか?弁護士が解説
Contents
相続放棄とは?
相続財産には、現金、不動産、預貯金などのプラス財産だけでなく、住宅ローンや借金などのマイナスの財産も含まれます。
そのため、マイナスの財産が、プラスの財産より多い場合は、相続財産を相続しないことができます。これを相続放棄といいます。
被相続人に多額の借金がある場合などでは、相続放棄を検討される方は多いですが、相続放棄の手続きを進める中で、被相続人と前妻との間の子など、面識のない人が相続人となっていることが判明したり、相続人の中に行方不明・音信不通となっている相続人がいる場合があります。
このような場合、どのように相続放棄の手続きを進めていけばよいでしょうか。
基本的には、以下でご説明するように、相続や相続放棄のルールを踏まえて、どのように対応するべきかを考えるのが有用です。
相続放棄の基本的なルール
相続放棄は相続人各人が単独で行う行為であること
相続放棄は、相続人各人が単独で行うことができ、相続人全員で行わなければならないわけではありません。したがって、相続人が複数人いる場合でも、基本的には、各相続人がそれぞれ、相続放棄するかどうかを検討し、各自で進めることができます。
例えば、被相続人に多額の借金がある場合、ある相続人は相続することを選択し、他の相続人は相続放棄することを選択することもできます。
このように、相続放棄するかどうかは、あくまで相続人本人が決めることであり、相続人本人以外の人物が勝手に決めることはできません。
相続放棄によって、相続人の範囲が変わること
・民法では、誰が、どういう順序で相続人となるのかについて、相続人の順位が定められています。
具体的には、①配偶者は常に相続人となり、②子、親・祖父母(直系尊属)、兄弟姉妹は、子が第一順位、直系尊属が第二順位、兄弟姉妹・甥姪が第三順位、という形で優先順位が決められています。そして、③相続人となるのは優先順位の高い人のみであり、先順位の人が1人でもいる場合には、後順位の人が相続人となることはありません。
・また、民法では、相続放棄を行うと、その人は最初から相続人ではなかったものと扱われると定められています。
そのため、例えば、被相続人の子が全て相続放棄を行った場合、第一順位の相続人がいないということになり、相続権が第二順位の相続人に移るということになります。
その上で、第二順位の相続人も全て相続放棄を行ったということになれば、今度は、第二順位の相続人がいないということになり、相続権が第三順位の相続人に移るということになります。
・以上をまとめると、相続人各人が相続放棄をした結果、同じ順位の相続人が誰もいなくなったという場合に限り、次の順位の人が相続人となるということになります。
相続放棄の期限
相続放棄は、自身のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に手続を行う必要があります。
この「自身のために相続の開始があったことを知った時」とは、原則として、被相続人となる人物が死亡した事実を知り、さらに、自身がその相続人となったことを知った時を意味します。
そのため、先ほどの例で、第一順位の相続人である子が全て相続放棄を行って、相続権が第二順位の相続人に移ったという場合、第二順位の相続人の「自身のために相続の開始があったことを知った時」とは、第一順位の相続人が全員相続放棄を行って、自身が相続人となったことを知った時を意味します。
したがって、次順位の相続人は、前順位の相続人が全員相続放棄をしたことを知った時から3か月以内の期限内に、相続放棄を行うことができることになります。
面識のない相続人がいる場合
以上が相続放棄の基本的なルールになります。
これを前提に、今まで面識のなかった相続人がいる場合の対応方法について、考えます。
・既にご説明しました通り、相続人が相続放棄を行うかどうかは、あくまでもその人自身が決めることです。
したがって、客観的に見て相続放棄をした方がよいと思われる場合や相続放棄をしてほしいと考える場合であっても、その人に相続放棄をするよう強制することはできず、あくまで相続放棄を打診することができるに留まります。
この場合には、その相続人に対して、相続が発生したことを知らせた上で、相続放棄を行うように促す連絡を取ることが考えられます。
その後は、基本的には、その方の判断に任せるのが穏当です。
・その後、その面識のない相続人が相続放棄を行って、同じ順位の相続人が全員相続放棄をしたということになれば、次の順位の人が相続人となります。
このとき、次の順位の人は、前の順位の人が全て相続放棄をしたことを知った時から3か月以内であれば、相続放棄を行うことができます。
他方、その面識のない相続人が、相続放棄をしないままに期限が過ぎてしまった場合には、その人が相続人として確定することになります。
そのため、この場合には、次の順位の人に相続権が移ることはありません。
音信不通・行方不明の相続人がいる場合
・この場合も、相続放棄を行うかどうかは、その行方不明・音信不通となっている相続人本人が決めることになります。
そのため、行方不明・音信不通の状態で連絡が取れない相続人が、相続放棄を行っていない限り、その方が相続人である状態に変わりはありません。
その行方不明・音信不通の相続人と同順位で相続放棄を行った人は、相続放棄によって相続人ではないことになりますし、相続人が次の順位に移ることもありません。
・もっとも、後順位の相続人が、被相続人の相続に関する心配を早々になくしておきたいといった事情から、行方不明・音信不通の相続人に早く相続放棄を行ってもらった上で、自身も早く相続放棄したいと考えられるようなケースもあります。
そのような場合、その行方不明・音信不通の相続人が従前の住所等に不在であるとして、家庭裁判所に不在者財産管理人の選任の申立てを行って、不在者財産管理人に相続放棄をしてもらうことが考えられます。
・ただし、不在者財産管理人の選任の申立てを行うためには、法律上の利害関係が必要とされています。
また、不在者財産の管理人の選任の申立てを行う際には、家庭裁判所に対して、少なくとも数十万円の金額を予納金として納める必要があり、基本的には、申立てを行う人が負担しなければなりません。
したがって、実際に不在者財産管理人の選任を行ってまで、相続放棄をするメリットがある場合はそれほど多くはないものと考えられます。
以上、相続放棄の基本的な考え方と、面識のない相続人や行方不明・音信不通の相続人がいる場合の対応方法について解説しました。
当事務所では、相続放棄の手続きの代理も行っております。
本件のような特別な事情の有無に関わらず、相続放棄全般について、お悩みの方は、是非一度ご相談ください。