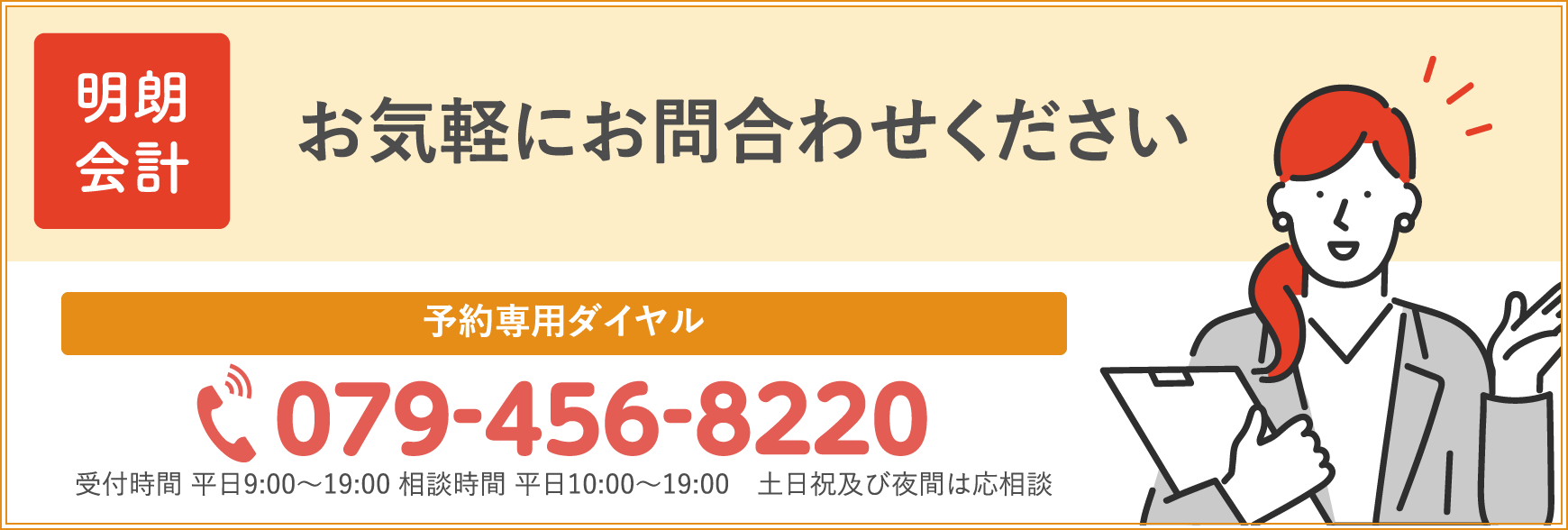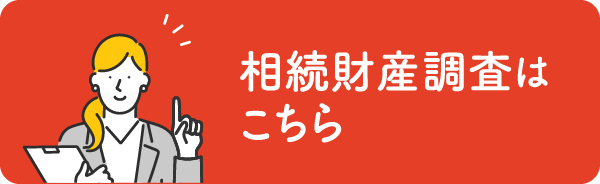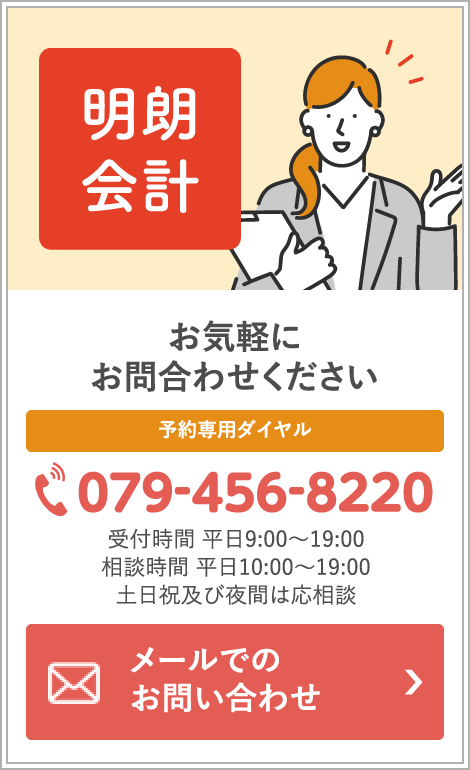相続手続きをおまかせしたい
相続の手続きについて
遺言がある場合
遺言とは、遺言者の生前の最終の意思を表した書面のことです。
遺言では、自分名義の財産について、誰に何を相続(承継、取得)させるか、自由に決めることができます。民法で定められた要式に従っていれば、遺言にどのようなことを書くかは基本的に自由です。
遺言が自筆証書遺言の場合は、家庭裁判所で検認を受ける必要があります。
また、公正証書遺言があるかどうかは、全国の公証人役場で遺言検索システムにて検索してもらうことができます。なお、公正証書遺言については、検認の必要はありません。
遺言の執行とは
遺言の執行とは、遺言内容を実現させるために、例えば預金の解約や不動産の名義移転など、さまざまな手続きをとることをいいます。
遺言ではそれを執行する職務を行う遺言執行者を指定できることになっています。また、遺言で遺言執行者を指定しなくても、第三者に遺言執行者の指定を委託することもできます。
なお、遺言執行者の指定は遺言の中だけで認められていて、故人の生前に取り決められていても無効です。
職務が複雑になると予想されるときは、遺言執行者を複数名指定しておくことも可能です。また、遺言で遺言執行者の指定を受けた人が辞退することも認められています。
遺言に指定がないときや、遺言執行者が辞退した場合などは、相続人や利害関係人が、家庭裁判所に遺言執行者の選任の請求をすることができます。
遺言執行者には誰がなっても良いのですが、高度な法律知識を要するので、弁護士等の法律の専門家に依頼するのが一般的です。
遺言の執行手続きについて
それでは、遺言執行者になった場合、どのような業務を行うことが求められるのでしょうか。
1)遺言者の財産目録を作る
財産を証明する通帳、登記簿謄本などをそろえて財産目録を作ります。
2)相続人に対し、遺言執行者就任及び任務開始の通知書を送付する。
遺言書の写しと財産目録を添付して、相続人に対し、遺言執行者就任及び任務開始の通知書を送付します。
3)遺言の内容に従い、相続手続を実行する
遺言の内容に沿って、実際に遺産を分配します。預金の名義変更、解約、分配や登記申請、債権回収、債務の弁済などを行います。
4)相続財産の不法占有者に対して明渡しや移転の請求をする
5)受遺者に遺産を引き渡す
遺言書の中に、相続人以外の第三者に財産を遺贈したいという希望がある場合は、その配分・指定にしたがって、遺産を引き渡します。その際、所有権移転の登記申請も行います。
6)認知の届出をする
認知の遺言があるときは、戸籍の届出をします。
7)相続人廃除、廃除の取消しを家庭裁判所に申し立てる
遺言執行者は以上のような職務を遂行していかなければなりません。
遺言執行者は、執行が完了するまでの間、すべての財産の管理権限を有していますが、調査、執行内容について、相続人に報告する義務があります。
遺言執行者が遺言執行の職務を終了したとき、相続人はそれに応じた報酬を遺言執行者に支払います。その報酬額は遺言でも指定できますが、家庭裁判所で定めることもできます。
遺言がない場合
遺言がない場合、被相続人が死亡時に有していた遺産について、個々の遺産を誰が取得するかを確定させる遺産分割の手続を取ることになります。
相続人調査
どの遺産を相続人のうちの誰が取得するかを確定させるためには、相続人が誰であるかが確定しなければ始まりませんので、相続人が誰であるかの調査を行うことが必要となります。
この調査を当事者本人が行う場合、役所に戸籍謄本類を請求し、戸籍謄本類を判読した上で、自身で相続人を確定していくことが必要となります。
もっとも、古い戸籍謄本類では内容の判読が難しいことも多く、また、相続関係が複雑でどこまで戸籍謄本類を集めればよいか分からないケースも少なくありません。
そのような場合、相続人間で遺産分割協議を行う前提として、弁護士に相続人調査を依頼することもできます。
相続財産調査
遺産分割を行うためには、相続人を確定することに加え、相続の対象となる相続財産の内容を確定する必要があります。
被相続人が生前、保有する資産の内容を明らかにしていれば問題ありませんが、そうでなければ相続人自身で調査することが必要となります。
そこで、代表的な相続財産である預貯金、有価証券、不動産について、その調査方法をご説明します。
1)預貯金、有価証券について
被相続人の保管していた通帳やキャッシュカード等をもとに、該当する金融機関に対し、残高証明書及び過去の取引明細(取引履歴)の発行を求めることになります。このとき、残高証明だけでなく、過去の取引明細を入手することも重要です。過去の取引明細を見ると、被相続人が生前、認知症等のため老人ホームで生活しており金銭管理や金銭の入出金ができない状態であったのに、頻繁に金銭が引き出されているなどして、他の相続人の使い込みの疑いが判明することがあるからです。金融機関にもよりますが、過去10年分の取引明細の入手が可能であることが多いです。
被相続人が保有していた通帳やキャッシュカードなどが見当たらない場合でも、被相続人が生前預金を有していたと思われる金融機関があれば、該当する金融機関に対し、預金の有無の照会をかけることも可能です。
株式等の有価証券については、証券会社から被相続人宛てに、定期的に取引レポート等が送付されていることが多いですので、これをもとに、当該証券会社等に対し、残高証明書の発行を求めることになります。
2)不動産について
被相続人宛てに役所から毎年送付されている固定資産税納税通知書や、被相続人が保管していた登記済権利証などをもとに、該当する不動産について、法務局で登記簿謄本を入手します。
また、被相続人が複数の不動産を保有していることが明らかであるものの、どのような不動産を保有しているかが分からない場合には、役所に対し、名寄帳の発行を求め、詳細を把握することになります。
代表的な相続財産の調査方法は以上のようなものになりますが、相続財産には様々なものが含まれるうえ、相続財産が多い場合、金融機関や証券会社、役所に対し、各書類の発行を申請するのも手間がかかり煩雑です。
相続財産調査をする時間がないという方や、煩雑な手続きは専門家に任せたいという方は、弁護士に相続財産調査を依頼することも可能です。
遺産分割協議
遺言がない場合には、相続人間で遺産分割の協議(話し合い)を行うことが必要となります。この遺産分割協議では、誰がどの遺産を取得するのかを相続人間の話し合いで自由に決めることができます。
ただし、一定の基準、指標がなければ円滑な話し合いが進まないことも多く、民法では、この基準、指標となるものとして、法定相続分が定められています。
遺産分割の手続
1)遺産分割協議
遺産分割協議とは、相続人の間で、誰がどの遺産を取得するかを協議(話し合い)によって決するものです。
協議が整えば、遺産分割協議書を作成し、それに基づき、預金の解約や不動産の登記等の相続手続を行います。
2)遺産分割調停・審判
遺産分割協議で話し合いが合意に至らなければ、家庭裁判所に遺産分割調停の申立てを行うことが考えられます。
遺産分割調停では、裁判所から選任された2名の調停委員が相続人の間に入り、遺産分割を成立させるために、話し合いの仲介を行います。遺産分割調停も話し合いを行う手続である点で遺産分割協議と共通する面がありますが、調停は中立的な第三者が間に入ることから、相続人だけで協議を行う場合よりも、遺産分割が成立する可能性が高まります。
調停で遺産分割の内容に合意ができれば、調停調書が作成されますので、それに基づいて、銀行の解約や不動産の登記等の相続手続を行うことが可能となります。
もっとも、遺産分割調停を行っても遺産分割の合意ができないこともあります。この場合、遺産分割調停は遺産分割審判に移行し、最終的には裁判官が遺産分割の内容を決定することになります。
名義変更手続き
遺産分割協議や調停・審判といった手続きを経て遺産分割の内容が確定した後は、確定した内容を実現するために、金融機関や証券会社等に連絡し、遺産を承継した相続人に名義変更を行うために必要とされる手続きを行うことになります。また、不動産については、法務局において、登記名義移転の手続きを行うことが必要になります。
相続手続きを弁護士に依頼するメリット
遺産分割紛争の長期化を避けることができる
他の相続人と遺産分割に関する意見が合わない場合、当事者同士で協議を行っても平行線となり、結局、合意できないまま年月だけが経過しているケースも少なくありません。
しかし、弁護士に依頼すれば、逐次、問題点に対する必要な措置が取られることで、紛争解決に向け前進していくことがほとんどですので、いつまでも紛争が解決しないということはありません。
当事者で話し合っても平行線になりそうな場合は、弁護士に依頼することで、紛争の長期化を避けることが期待できます。
相手方と直接話をする必要がなくなる
遺産分割は、相続人という身近な親族間で行うものでありますが、遺産分割協議が上手くいかないということは親族間で対立関係を生じていることになりますので、交渉を続けること自体が大変な精神的ストレスとなります。
しかし、弁護士に依頼すれば、相手方との交渉を全面的に弁護士に委ねられるため、こういったストレスを軽減することができます。
なお、遺産分割協議は当事者だけで行い、合意できずに遺産分割調停や遺産分割審判の申立を行うといったケースでも、調停や審判からでも弁護士に依頼すれば、手続に不慣れな当事者ご本人のために、十分なサポートを期待することができます。
遺産の内容や相続人の調査ができる
そもそも遺産の内容や相続人が誰であるかについて、最初から分かっていることもありますが、全く分からないこともあります。相続人の一部が他の相続人に遺産の内容を明らかにしないということもよくあります。
こういった場合には、弁護士が相続人の戸籍謄本類や、銀行等金融機関の取引履歴等を取得し、相続人や遺産の内容を確定させることができます。
また、例えば銀行の取引履歴等を取得するなどの財産調査の過程で、他の相続人の特別受益が判明することもあります。
妥当な分割案を検討することができる
遺産の内容がどのようなものであるかという点や、法定相続分がいくらであるかという点については、ご本人だけでも調べることができるかもしれません。
しかし、特別受益や寄与分が問題となるのではないかと疑われる場合などには、法的な観点からの検討が不可欠となります。
したがって、そのような場合は、弁護士に依頼することで、適切なアドバイスを得て、妥当な遺産分割を実現することが可能となります。
遺留分の侵害があるかどうか検討し、侵害された遺留分を取り戻すことができる
遺言により特定の相続人が多くの遺産を承継することになる場合において、遺産の内容が複雑であったり、遺産の財産的価値の評価が難しいなどの理由により、自身の遺留分の侵害の有無を判断することが難しいケースでも、弁護士に依頼することで、専門的見地からのアドバイスを得て、遺留分侵害の有無を検討し、侵害された遺留分を取り戻すことが可能となります。
弁護士に依頼すべきケースとは
弁護士に依頼するメリットは上で述べた通りですが、弁護士に依頼すべきケースとして、典型的なものは以下のようなケースです。
- 自分の相続分が少なくなる内容の遺産分割に応じるよう、他の相続人から強く求められているが、納得できないため協議が平行線となっているケース
- 相続人間の仲が悪く、意思疎通が極めて難しいケース
- 他の相続人が被相続人から贈与を受けているケース
- 他の相続人による遺産の使い込みが疑われるケース
- 遺言により、自身の遺留分の侵害が疑われるケース
以上のようなケースでは、当事者間で協議を続けても、そもそも協議自体が進まず、納得できる解決に至らないことが多いため、弁護士に依頼することによるメリットを最も感じられるケースといえます。また、早期に依頼することで、紛争が先鋭化することを回避することも期待できます。
当事務所では、相続問題に詳しい弁護士が対応しております。相続問題でお悩みの方は、紛争が複雑化する前に、早めにご相談されることをお勧めします。